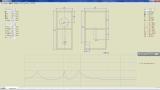タグクラウド(登録数順)
古舘@横浜 さんの日記
裸での音出しでは余り良く分からないので、何か装着出来る箱が無いかと物色すると、6年ほど前に1インチや2インチでどこまで低音が出せるかの検討をしていた時に作ったTQWT箱のバッフルを入れ替えれば出来そうなので、それ用の専用バッフルを作ることにした。
ユニットの取り付け穴は54mmで2 1/8インチのホールソーがピッタリであったが、更に外径が67mmで手持ちの2 5/8インチのホールソーがピッタリなのを見付け、フレームのフランジ部分をバッフルに埋めれそうなので、その確認も兼ねてバッフルの加工をした。案の定、取り付け穴も外形もピッタリで殆ど隙間が無く収まった。
付属の取り付けネジは3mmの木ネジで普段余り使わないサイズだが、下手に2mm程度の下穴を開けてしまうとすぐバカになってしまいそうだ。大きくても1.8mm程度の下穴が良さそうだ。私は1.5mmのドリルがあったのでこれで下穴を開けたが丁度良かった。
バッフルのスピーカー取り付け穴以外はバッフル取り付け用のネジ穴を開けて配線材を仮ハンダ付けすると音出しが出来る様になった。
元々の箱はTQWT方式で約145cmの管長を四つ折りの構造で、共振周波数はおよそ70Hz位になると思われるが、実際にも80Hzまではフラット、63Hzがそこから10dB落ちになっており、計算通り。
1インチの時は音道をドライブし切れないのか大分レベルが低かったが2インチだとやはり違う。
実際に聴いてもウッドベースなど、かなりの低い音まで再生している。発表のf特にある、5kHzからの落ち込みはそれほど感じられないが、音の立ち上がりが良いとは言えないので、ここら辺の特性が影響しているのかも知れない。f特を取っても10kHz付近で落ち込んではいるものの素直に高域まで伸びている。音質的には明るく弾ける音ではないが、落ち着いた音で静かにしっとり聴くには良いと思う。
400Hz付近に大きなディップがあるが、これは箱の問題のようで1インチの時も同じように出ていたので何らかの対策が必要かも知れない。
一番の欠点は、小型スピーカーの弱点でもあるのだが、パワーが入らず、ボリュームを上げると歪っぽくなる。デスクトップのニアフィールドで聴くには十分だが、ちょっと広い場所や大きな音で聴くには向いていない。
結論:TQWTで何とか行けそうなことは分かったので、本番では幅を20mm程広くしてサイズも一回り大きくして作ろうかと思う。
コメント一覧
投稿ツリー
たてちゅうさん
当時は手抜きせずに何回も磨いては塗って磨いては塗ってを繰り返していました。
作り直すよりこのまま出品した方が出来が良いかも知れません ![[worried]](/modules/xpwiki/image/face/worried.png)
今度は共鳴管に挑戦ですか!? どんなのが出来るか楽しみです。
古舘さん
立派な箱がありましたね。
今日は朝からエージングCDをボリュームを12時あたりまであげてガンガン鳴らして鍛えています。
(毛布でぐるぐる巻き)
そこそこ鍛えたので聴いてますが、このユニットPC用にもってこいの感じ。
超ニアフィールドで聴くにはとてもよさそう。
ビートルズを聴きながらキーボード叩いてますがボーカル、コーラスは画面中央奥、ギター左、ドラムは右にきれいに分離してます。
古舘さんはどの方式になりますかね?
kenbeさんツインユニットでバックロードホーンで鳴らしてますが納得してないようです。
関西の「下手の横好き」さんはマルチバスレフ。
無くならないうちにもう一組買ってこよう。
コニさん
昨日の感想は、片チャンネルで吸音材なしでの感動でした。
ステレオにして、吸音材を詰めたら聴き易くなっています。
もう少し、エージングをするつもりでいます。
コニさん
随分気に入ったみたいですね 
小さいユニットだと1組増えてもそんなに邪魔にならないのが良いですね。
皆さん、色々な方式で試しているようですね。
マイルスTKさんは、ダンボールバックロードで作っていますね。
私のは本文に記載しましたがTQWT(Tapered Quarter Wave Tube)方式になります。
これ自体の構造写真は見当たらないのですが、同時期に作ったTQWTの組立て前の写真を載せておきます。音道四つ折りの構造自体は同じです。
[添付]
また、祝勝会(残念会!?)で聴き比べ会をしましょう 
Kenbeさん
発売日の二日後には立派なバックロードが形になっているのには今更ながら驚きました。
私はその間に小さなバッフルを交換するだけでした 
3時過ぎから車の1ヶ月点検に神奈川SUBARUに行ってきました。
帰宅は7時過ぎ、その間エージングCD廻しっぱなし、おかげでエージングが進みました。
ダクトに詰めたウェスを取り除いてもボン付きが気にならないレベルになった。
DSD音源で聴いてますがバランスよく鳴ってます。
低音はしれてますが。(80Hzくらいかな)
kenbeさん
そうだったんですか、エージングが進むといいですよ。
昨年のより気に入ってます。
↑
これワタシです。ゲストで投稿しちゃいました。
古舘さん
今年は応募しませんが聞き比べ大会是非またやりましょう。
こんばんは
コニさんはTQWTなんですね。
天板?の厚さがすごそうですね
私はインパクト勝負の作品です。
マイルスTKさん
こんばんは
TQWTは古舘さんのです、ワタシ木工苦手でとてもこんな難しいのできません ![[worried]](/modules/xpwiki/image/face/worried.png)
古舘さん、みなさんこんにちは。
皆さん、早速進んでますねー。 私も19日に届きましたが当分仕事オンリー+ほんの少しの家族サービスで手いっぱいで、眺めるので精一杯・・
皆さんの作品の経過と完成を楽しみにしていますねー。 
コニさん
失礼しました
あまり確認しないで
「おおー、ついに」と思ってしまいました。
古館さん、
今年は「匠」部門への応募になりますね。
私は、一般から頑張ってみます
なーおさん
お仕事、忙しくて大変ですね。
時間が合えば聴き比べ会、ご一緒しましょう。
マイルスTKさん
残念ながら、匠の要素が一つも見当たりません ![[worried]](/modules/xpwiki/image/face/worried.png)
まだ設計の段階ですが、一般で参加かと…
おっと、参加の規定を読むと、過去に受賞歴がある人は強制的に匠での応募になるのですね 
一気にハードルが上がりました 
古舘さん、
そうなんです。
この「匠」部門の応募規定を見て、
ちょっとがんばる気が出てきました。
ただ、賞の数は増えないかもしれないので、どちらのカテゴリーでも競争は激しいですよね。
マイルスTKさん
匠部門にはどんなに頑張っても越えられない塗装や工作の技術を持った「匠」が大勢居るので、日曜大工に毛が生えた程度の私にはとても厳しいです。 
いくら良い音の作品が出来たとしても、それ以前の仕上げ、デザイン、アイデアなどで特筆したものがないと、聴いて貰うステージにも上がれません。
如何に書類選考時点で審査員の方々の興味や目を引く事が出来るかが取り敢えずの目標になりますね。
昨年、石田善之先生が「誰にも出来る」を選考基準の一つに上げていましたが、匠部門ではそれは外されるのでしょうかねぇ?!
今一選考基準がはっきりしないのでアプローチも難しいですね 
一般部門といっても応募者はそれなりに多いと思われますので、簡単ではないと思いますがチャンスもありますね。
頑張って来年は厳しい匠の世界にようこそ 
新しくコメントをつける
投稿者
カテゴリー
月表示
新着日記
- オフ会選曲リスト [05-01 22:44]
- オフ会用スピーカー その10 [04-22 04:04]
- オフ会用スピーカー その9 [04-19 04:25]
- オフ会スピーカー その8 [04-18 04:39]
- オフ会スピーカー その7 [04-16 03:32]
- オフ会スピーカー その6 [04-10 04:30]
- オフ会スピーカー その5 (ネットワーク編) [04-03 04:23]
- オフ会スピーカー その4 [04-01 04:23]
- オフ会スピーカー その3 [03-28 03:24]
- オフ会用スピーカー その2 [03-26 23:07]
新着コメント
- Re: オフ会用スピーカー その10 古舘@横浜 [04-22 11:16]
- Re: オフ会用スピーカー その10 たてちゅう [04-22 10:09]
- Re: オフ会用スピーカー その9 古舘@横浜 [04-20 02:06]
- Re: オフ会用スピーカー その9 N.H [04-20 01:34]
- Re: オフ会用スピーカー その9 古舘@横浜 [04-20 01:17]
- Re: オフ会用スピーカー その9 N.H [04-20 00:48]
- Re: オフ会用スピーカー その9 古舘@横浜 [04-20 00:29]
- Re: オフ会用スピーカー その9 N.H [04-19 23:48]
- Re: オフ会スピーカー その8 古舘@横浜 [04-18 20:41]
- Re: オフ会スピーカー その8 N.H [04-18 11:50]


 前の日記
前の日記