ページ内コンテンツ[4]
- ダブルバスレフ
- 特徴
- 計算式
- 周波数とインピーダンス特性
- 派生形
ダブルバスレフ  [5]
[5]
バスレフ[6]スピーカー[7]の一種で、一般的なバスレフ[6]は1つの空気室と1つのバスレフ[6]ダクトを持つのに対して、ダブルバスレフは2つの空気室と2つのダクトを、直列で組み合わせたような形態を持つ。
特徴  [8]
[8]
元々、ダブルバスレフは長岡鉄男氏が考案したか実用化した方式で、最低域は延びるものの、第1ダクトの輻射音圧が第2空気室と第2ダクトから漏れ聞こえてくるという構成上、どうしても音圧不足になりがち。 また、音質的には甘めの傾向がある。
計算式  [9]
[9]
ダブルバスレフも、以下のバスレフ[6]の計算式を組み合わせて計算できます。
Fd=160√(S/Vc(L+r)) [Hz]
これをダブルバスレフにすると、
Fd1=160√(S1/Vc1(L1+r1)) [Hz] Fd2=160√(S2/(Vc1+Vc2) x (L2+r2)) [Hz]
- S1,S2=第1ダクト、第2ダクトの面積(cm^2)
- L1,L2=第1ダクト、第2ダクトの長さ(cm)
- r1,r2=第1ダクト、第2ダクトの半径、または半径換算値(cm)
- Vc1,Vc2=第1空気室、第2空気室の実効内容積(リットル)
ポイントは、第2ダクトの計算では、第1空気室と第2空気室の容量の合計、つまりスピーカー[7]全体の空気量からダクト分などを差し引いた全体有効容積を使う点です。
一般的に、Fd1 = 2 x Fd2 あたりがバランスを取りやすいでしょう。
周波数が2倍、ということは、第1ダクトの共振は第2ダクト共振の1オクターブ高い周波数ということです。
記憶を頼りに書けば、V2≒2V1~2.5V1 あたりが適切、と長岡鉄男氏が布教していたように思います。
Last-modified: 2009-05-20 (水) 00:02:44 (JST) (2329d) by 庶務係
Links list
(This host) = http://www.enbisp.com
- (This host)/modules/xpwiki/91.html
- (This host)/modules/xpwiki/89.html
- (This host)/modules/xpwiki/88.html
- (This host)/modules/xpwiki/
- (This host)/modules/xpwiki/53.html#g35ca477
- (This host)/modules/xpwiki/52.html
- (This host)/modules/xpwiki/87.html
- (This host)/modules/xpwiki/53.html#i18dd9ed
- (This host)/modules/xpwiki/53.html#l4591f68
- (This host)/modules/xpwiki/153.html
- (This host)/modules/xpwiki/53.html#ne7d6721
- (This host)/modules/xpwiki/gate.php?way=ref&_nodos&_noumb&page=%E7%94%A8%E8%AA%9E%E9%9B%86%2F%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%2F%E3%83%80%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%90%E3%82%B9%E3%83%AC%E3%83%95&src=d-bassreff.gif
- (This host)/modules/xpwiki/53.html#ge689818
- (This host)/modules/xpwiki/77.html
- (This host)/modules/xpwiki/59.html
![[PukiWiki] [PukiWiki]](http://www.enbisp.com/modules/xpwiki/image/pukiwiki.png)
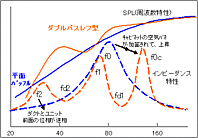 [12]
[12]